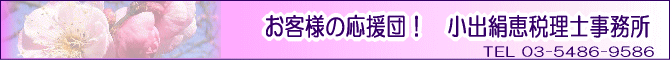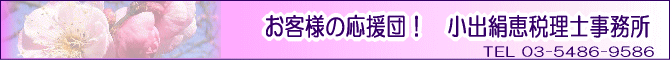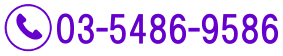|
会社法が5月1日から施行されました。
「有限会社がなくなる?」「登記が必要?」
今月は、会社法施行が中小企業に及ぼす影響について考えます。
| Q1.有限会社はなくなるの? |
| A1 |
これからは、有限会社という会社類型がなくなるわけですから、有限会社の設立はできなくなります。
しかし、すでにある有限会社は、現在の社名の「有限会社○○」または、「△△有限会社」という名称のまま存続(特例有限会社)できます。
ただし、法律上は株式会社になりますので、
「社員」「持分」「出資1口」は、それぞれ「株主」「株式」「1株」となり、
有限会社の資本の総額を出資1口の金額で除した数が
株式会社の発行済株式の総数となります。
◆例えば、
資本の総額300万円、出資1口1,000円の有限会社の場合には、
資本金の額300万円、発行済株式の総数 3,000株(=3,000,000円÷1,000円)となります。
口数ではなく、株数になるわけです。
もっとも、上記は会社が登記する必要はありません。これに必要な登記は、登記官が職権で行うことになっています。 |
|
| Q2.有限会社を株式会社にするにはどうすればいいの? |
| A2 |
登記が必要になります。
株主総会によって、「有限会社○○(または△△有限会社)」を「株式会社○○(または△△株式会社)」という商号に変更する決議をし、株式会社の設立の登記の申請と特例有限会社の解散の登記の申請を行う必要があります。
ところで、その場合の会社の税金のことですが、登記費用(印紙税等)はかかりますが、法人税や消費税等の会社の税金については、単なる商号変更手続の一貫として、解散も設立もなかったものとして扱われますから、税務上の影響はありませんので、ご心配なく。 |
|
| Q3.役員の任期は? |
| A3 |
株式会社には、役員の任期が定められています。
施行された会社法でも、原則として取締役の任期は2年、監査役の任期は4年です。
しかし、株式の譲渡制限を設けている会社(中小企業のほとんど)にあっては、定款で定めることによって、最長10年まで取締役及び監査役の任期を伸ばすことができるようになりました。
謄本の最後の部分に「株式を譲渡する場合には、取締役会の決議を要する。」旨の一文があれば、これが、株式の譲渡制限の規定です。 |
|
| Q4.確認会社はどうすればいい? |
| A4 |
最低資本金規制が廃止されたことに伴い、確認会社(1円会社等の改正前の最低資本金を満たさないで設立された会社)も、増資をする必要がなくなりました。
しかし、確認会社は、設立後5年以内に増資ができなかった場合には解散する旨の登記がなされておりますので、取締役会で定款を変更して、その解散する旨の規定を変更し、解散の事由の登記を抹消する登記申請をすることによって、会社を存続させることができます。 |
|
| Q5.登記は必要なの? |
| A5 |
Q1でもとりあげていますが、会社法の施行により必要となる登記のほとんどは、登記官により職権でなされますから、特に登記は必要ありません。
(ただし、登記の必要な場合もありますから、司法書士や税理士にご相談ください。)
既存の有限会社の多くが、当面はそのまま様子見ではないでしょうか。会社も「有限会社○○」のままですし、役員の規定も、任期がないことも、今までの有限会社に適用されていた規定は、そのまま適用されます。株式会社を名乗りたいという場合は、上記Q2の手続きが必要ですが、当面有限会社のままでいいという場合には、特に何もする必要はありません。
株式会社の場合も、いままでどおりで良いというのであれば、特に登記を要しない場合がほとんどです。取締役等の任期を10年にする場合も定款変更だけで、その旨の登記は必要ありません。
しかし、せっかく会社法の施行で機関設計が定款の定めによって自由にできるようになったのですから、この際、名ばかりの取締役や監査役を設置は止めて、実体に即した簡素な組織体制にするということも可能です。
たとえば、取締役は社長だけ。監査役は置かず、取締役会も設置しない。取締役の任期は10年にするという具合です。
役員改選のタイミングに合わせて、役員の任期満了の前に定款を変更します。取締役の任期を10年、取締役の人数を一人以上と改め、取締役会と監査役会を設置しないという条項も入れます。
その上で、任期満了による役員の選任と取締役会及び監査役会を設置しない会社である旨の登記をします。
任期10年との定款変更後の選任ですから、改選後の取締役の任期は10年になります。
会計参与を設置する場合にもその旨の決議と登記が必要です。 |
◆同族会社の多くに影響がある税制改正
平成18年4月1日以後開始する事業年度より、実質一人会社の社長報酬に対する給与所得控除額が損金不算入となるという法人税の改正がありました。
この場合の「実質一人会社」とは、役員及び同族関係者等が発行済株式総数の90%以上を保有し、かつ常勤役員の過半数を占める会社を言います。ただし、以下の場合には、いままでどおり損金算入することができます。
○社長の報酬と会社の所得の合計額の直前3年以内の
平均額が年800万円以下である場合
○上記の平均額が年800万円超3,000万円以下で
その平均額に占める社長報酬の割合が50%以下の場合
ポイントは、前3年間、会社の所得と役員報酬のうちの社長の分だけです。この影響は大きいと思います。
ちなみに、社長が2,000万円の役員報酬を受け取っておられる場合には、給与所得控除額は270万円ですから、法人税、法人住民税・事業税でその約3割、80万円強の増税になります。
逆に一定の要件を満たせば役員賞与が損金算入できるようになりました。会社法、税法、今年は大きな改正がいっぱいです。
詳細はこちらから小出絹恵税理士事務所にお尋ねください。
このページのトップへ
|